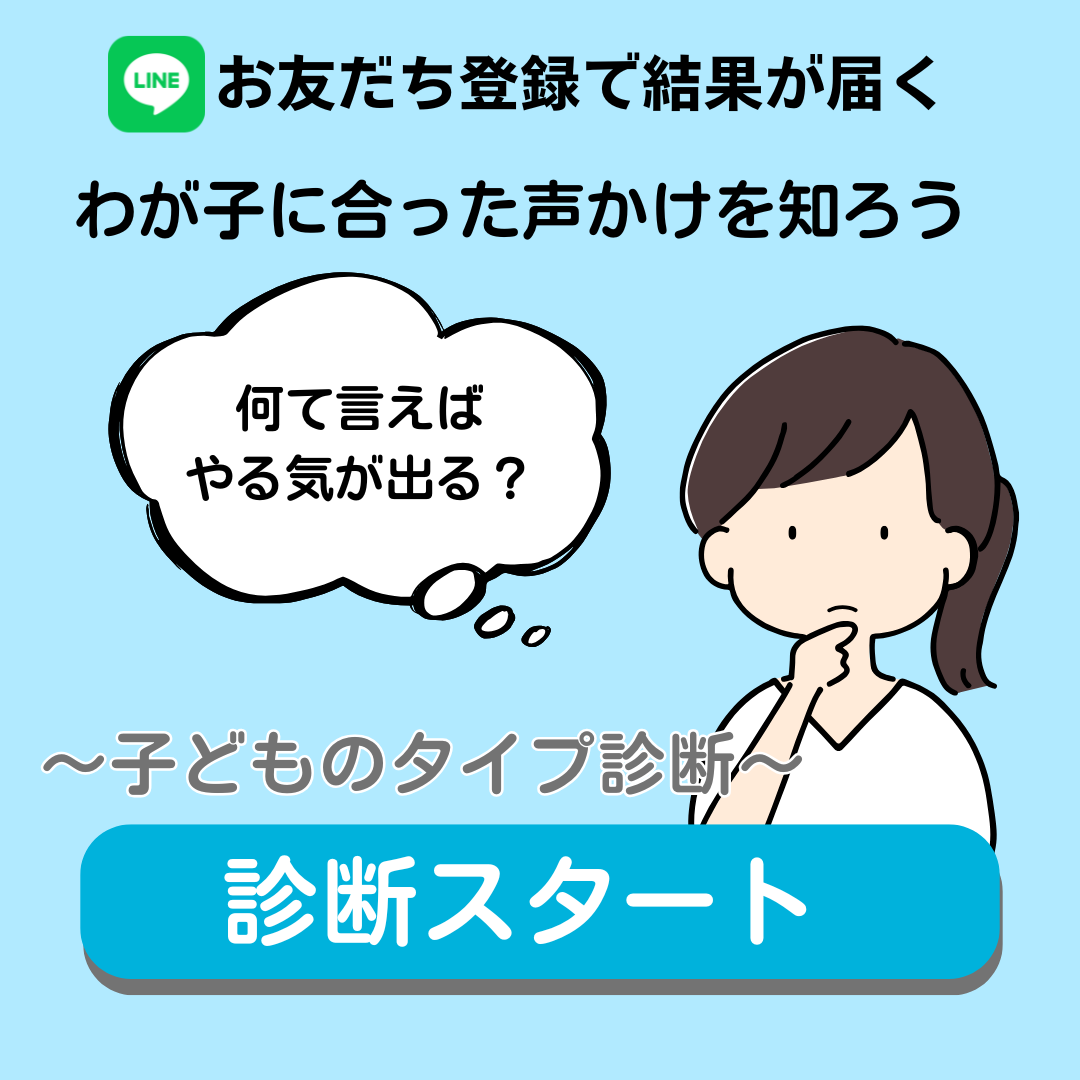考える力
【サッカー用語解説】アディショナルタイム(ロスタイム)とは? サッカーで使われる言葉の意味や違いを解説
公開:2013年7月17日 更新:2024年6月28日

■試合が止まっていた時間=「ロスタイム」
そもそも国際的にはアディショナルタイムと呼ばれるものがなぜ日本ではロスタイムと呼ばれるようになったのでしょうか?
ロスタイムは英語の「Loss of time」からきているといわれています。サッカーの試合時間は前半45分、後半45分の原則90分です(大人のサッカーの場合)。
主審の判断で時計が止められる時間、交代や負傷者が出た際に"失われた"時間を、実際のプレー時間から引いて両チームに公平になるようにしようというものです。
これは実際プレーした時間を基準に"失われた時間"つまりロスタイムを引いてちょうど90分という考え方です。
■「アディショナルタイム」とは「加えられる時間」
一方、「アディショナルタイム」の方は「Additional=加えられた」時間ですから、あくまでもキックオフから90分、そこから加えられる時間という目線です。
「ロスタイム」と「アディショナルタイム」どっちでも同じじゃない?
そんな声も聞こえてきそうですが、サッカーの世界の用語は「なるべくポジティブな言葉を使おう」という潮流があります。Jリーグで一時採用されていた、延長戦で1点先取するとその場で試合が終わり、先取点を挙げたチームの勝利になる「サドンデス」も「Vゴール」(のちにFIFAによって「ゴールデンゴール」として採用)に言い換えられた事例もあります。
サドンデス=sudden death(突然死)という響きが良くないとの判断でした。いまでもPK戦ではサドンデス方式と言ったりしますが、あまり積極的に"死"という言葉を使いたくないというのが本音のようです。
<結論>
ロスタイム
サッカーやラグビーなど競技時間が定まっているスポーツの試合で、負傷者の手当の時間など、競技時間としては勘定しない時間のこと。
主審の判断で、その時間の分だけ試合を延長する。
アディショナルタイム
意味はロスタイムと同じ。2010年7月16日の審判委員会にて名称を「アディショナルタイム」とすることを決定した