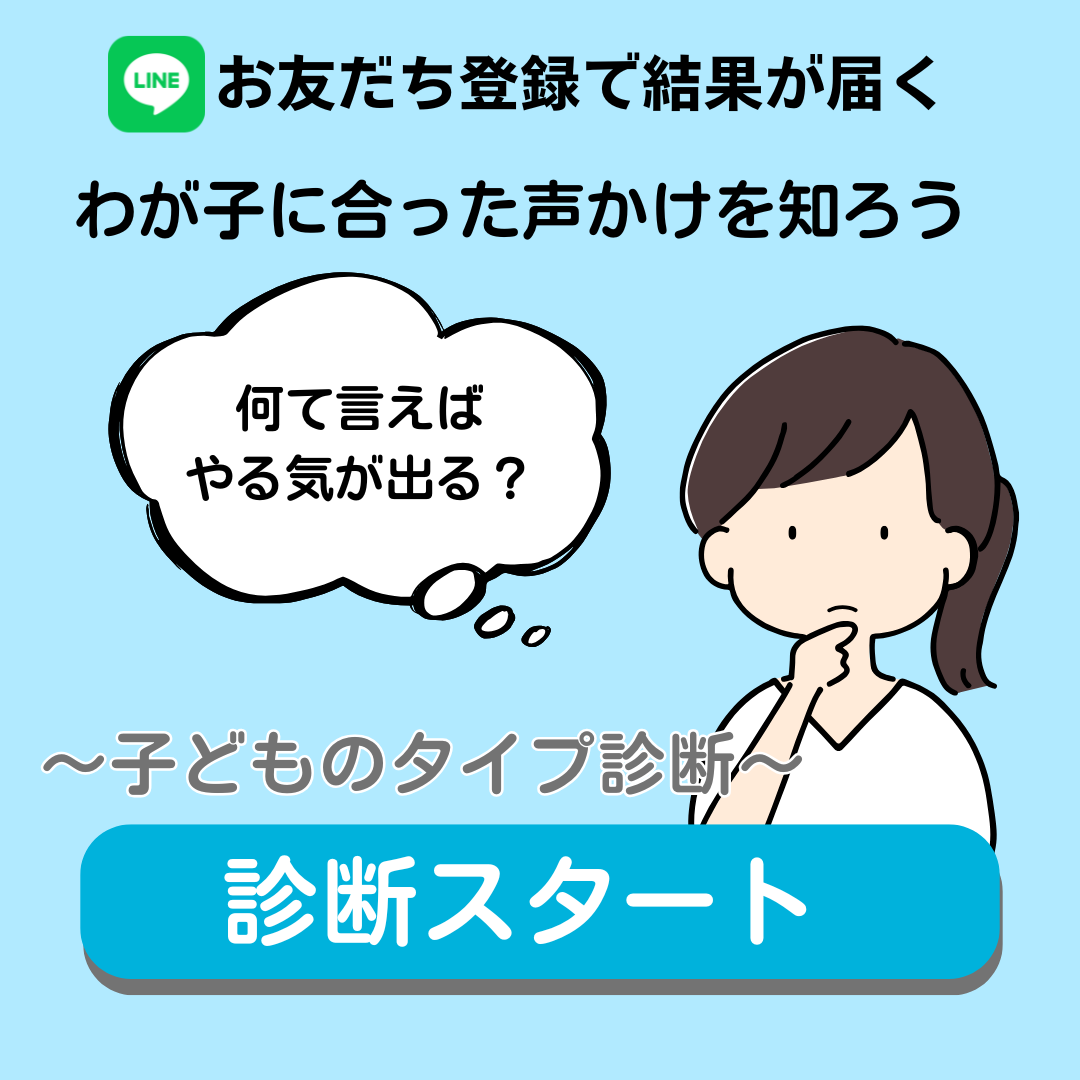- サカイク
- 連載
- 子どもが心からサッカーを楽しむための「サカイク10か条」
- 「子どもの力を信じて、先回りせずに見守ろう」の真の意味。 改めて考えたい、子どもの力と親自身のこと
子どもが心からサッカーを楽しむための「サカイク10か条」
「子どもの力を信じて、先回りせずに見守ろう」の真の意味。 改めて考えたい、子どもの力と親自身のこと
公開:2018年4月23日 更新:2025年4月14日
子どもは「自分で考えてプレーする」ことでサッカーの楽しさを感じて、誰かにやらされるのではなく、自分自身でどんどんチャレンジしていくようになります。そんな考えに基づいて、サカイクでは「サッカーを心から楽しむ子どもを増やす」ために、保護者の皆さんに様々なメッセージを発信してきました。
その一つが、保護者の皆さんに大切にしてほしい"親の心得"をまとめた「サカイク10か条」です。
ここでは、その10か条でも触れている「子どもの力を信じて、先回りせずに見守ろう」というテーマを改めて掘り下げることで、「先回りしない」という考え方の真の意味を探っていきたいと思います。
取材にご協力いただいたのは「シンキングサッカースクール」や「サカイクキャンプ」でコーチを務める高峯弘樹さん。そのお話の中には、保護者の方々にとって見逃せない"意外な"ポイントがありました。
(取材・文:本田好伸)
子どもが心からサッカーを楽しむための「サカイク10か条」1.子どもがサッカーを楽しむことを最優先に考えよう2.今日の結果ではなく、子どもの未来に目を向けよう3.子どもの力を信じて、先回りせずに見守ろう4.子どもは小さな大人ではないことを理解しよう5.コーチやクラブの考えを聞いてみよう6.ダメ出しや指示ではなく、ポジティブな応援をしよう7.あなたが子どもの良いお手本になろう8.子どもの健康や安全に気を配ろう9.サッカー以外のことを大切にしよう10.笑顔で子どもとサッカーを楽しもう
■放任ではなく、ギリギリまで手を出さない
サッカーに限らず、子どもが何事に対しても自分で考えて、判断して、決断して、行動していけるようになるためには、親が先回りしないで見守ることが大切──。
サカイク10か条でもお伝えしているように、こうした考え方が大切ということを頭では理解しているつもりでも、子どもの前ではついつい手を出したり、行動を促してしまったりすることはないでしょうか?
「分かっているけど言ってしまう」というのは、誰にでもあることでしょう。でも改めて考えないといけないのは、先回りすることが、子どもにとってプラスに作用するケースが多くはないということです。
以前、メンタルトレーナーの大儀見浩介さんに取材した際、こんなことを話していました。「人がやる気をなくす瞬間とは、自己決定して行動を起こした直後に、外からの刺激が入ってしまうこと。例えば、親からこうしろ、ああしろと言われてしまうというように」。つまり、自分で考えて行動しようとしている時に、親からあれこれ言われてしまうことは、子どもがやる気を失ってしまう大きな原因となるのです。
そうした意味でも、「子どもの力を信じて、先回りせずに見守ろう」というテーマの重要性を理解していただけると思います。ただそうは言っても、うまくできない......。それは、どうしてなのでしょうか。
「放っておきなさいと言われても、親としては、正解はこうじゃないかと伝えたくなってしまいます。それに、周囲の評価が気になるということもあるでしょう。他の子はこれができるのに、うちの子はしなくていいのだろうか、親同士で話している中で、どうしても自分の子どもと他の子どもを比較してしまう......。そういうこともあると思います。でも、それでは子どもが窮屈に感じてしまうかもしれません」
高峯コーチが伝えたかったのは、「子供は親の所有物ではなくて別の人格を持った人間だということ。だから、出来るだけそれを尊重してあげないといけない」ということです。「子どもだから放っておけない」と考える気持ちがあるのであれば、「言いたいのを辛抱、我慢して、意識的に距離を取って見守る」ということを心掛ける必要があるようです。

この「放っておく」ということが、「先回りしないで見守る」ための重要な考え方です。
「これは『放任』ではなく、『ギリギリまで手を出さない』ということです。私がよく例に出す話があるのですが、子どもがはじめて自分一人でまたは兄弟などとご近所へお使いに行くテレビ番組がありますよね? そこで登場する『カメラマンと子ども』の距離感が理想的なんです。カメラマンは、子どもが困って泣いていても、転んでも、付かず離れずの距離で見守っています。心配だから手を出したいけど、自分はカメラマンだからとちゃんと"放っておいて"、ちゃんと見ていてあげる。そういう距離感が、子どもと親の間には必要なのではないかと思います」
例えば、殆どの親御さんは自分の子供が、自分で考えて行動出来る子になって欲しいと思っていると思います。それならどの様に子供と接したら、そのように育つのかを考えてみるべきですね。常に何かを与えられる環境で果たして自分で考え、行動してみるという習慣がつくでしょうか。大人と同じで子供も自分で決めたい、自分でやりたいのです。
例えば2歳くらいの子どもでも、ふとした時から「自分で!」と主張するようになりますが、その頃にはもう自我が芽生えていて、自分でやり切るという意思表示をしています。だからこそ親は、子どものそういう意志を尊重して、彼らなりに考えて行動する姿を、先回りしないで見守ってあげないといけないのです。
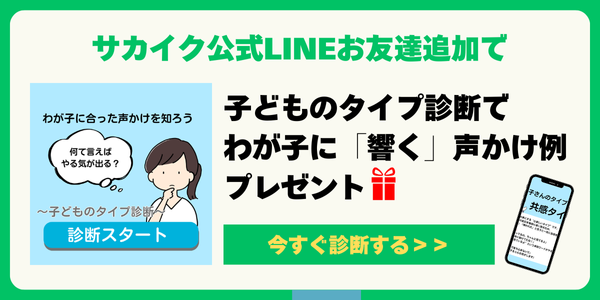
■子どもの自立を促すための、夫婦関係の重要性?
高峯さんは、「こうしたことを実践するためにも、まずは夫婦関係を見直してはどうでしょうか?」と言います。少し意外かもしれないですが、親と子どもの距離感を考える上でとても大切なことのようです。
「母親も父親も、子育てということにおいては対等な関係ですよね。夫婦関係はもちろん、外の人が口を挟むことではないのですが、子どもとどのように関わっていくかを考えていくためには、夫婦できちんとコミュニケーションを図って、互いの価値観をすり合わせていく必要があるのではないかと思います」
高峯さんはこの「夫婦のコミュニケーション」の重要性を強調します。母親も父親も、それぞれの親の元で育ってきた環境や、周囲の大人との関係の中で成長してきた経験があるために、子どもとどのように接するかという価値観は、得てして異なるものです。でも、本当に我が子の成長を考えるのであれば、両親が同じような方向を見ていないで子どもと接していては、彼らにとっては弊害となってしまうかもしれないのです。
だからこそ、どちらかが子どもに「ああしろ、こうしろ」と言い過ぎてしまっていると感じたら、「自分で考えて始めるまで待ってみよう」と、あれもこれもと先回りして準備するような関わり方が見られたら、「もう少し放っておいてあげてもいいんじゃないかな」と、「他の子はこれができる」とか「○○くんの親から、これをしてないの? と言われた」という話があったら、「じゃあ、うちの子がどんなことをしたいのか聞いてみよう」というように、相手に伝えてあげるといいのではないでしょうか。
子どもには子どもの人生があると言いましたが、親にも親の人生があります。「もし、『子育てが趣味』となってしまっているようなら、子育て以外に楽しめるものを見付けることも、子どもとうまく距離を取れるようになるかもしれません。それに、仲の良い夫婦関係であれば、それを見た子どもも幸せな気分になれますよね。子どももそういう姿を見て育って、いずれ親になりますからね」
夫婦が同じ方向を見て子どもと接するようになり、子どもといい距離感を保てていれば、子どもから自然に親の方へと歩み寄って来るようになります。「もっとうまくなるためにこれをしたい」とか、「今度はこういうことにもチャレンジしたい」とか、子どもが自ら「やりたい」という思いを伝えてきたら、その時こそ、サポート役としての親の出番です。それまで親は、ジッと見守っていてあげることが大切なのです。
「社会生活のルールなどを伝える時には当然親の強制も必要です。でも子供にやらせることだけではなく、『どうしたら自分でやりたいという気持ちになるのだろう』と考えること。親は、子どもに何かを与えるよりも、子どもが自分でやりたいと言えて、しかもそれが出来る環境を作ってあげる方向にもっともっとエネルギーを注いで欲しいですね。それはとても難しい事だと思います。むしろ何かを与えてしまう方が簡単です。でもそこできちんと考えて子どもと接してあげることこそ、親がしなくてはいけないことですよね」
ギリギリまで手を出さずに放っておく。夫婦で子どもとの接し方のコミュニケーションを図る。高峯さんの言葉から感じるのは、子どもの自立には、何よりも親の自立こそが必要なのだろうということでした。
募集中サカイクイベント
関連記事
子どもが心からサッカーを楽しむための「サカイク10か条」コンテンツ一覧へ(6件)
コメント
- サカイク
- 連載
- 子どもが心からサッカーを楽しむための「サカイク10か条」
- 「子どもの力を信じて、先回りせずに見守ろう」の真の意味。 改めて考えたい、子どもの力と親自身のこと