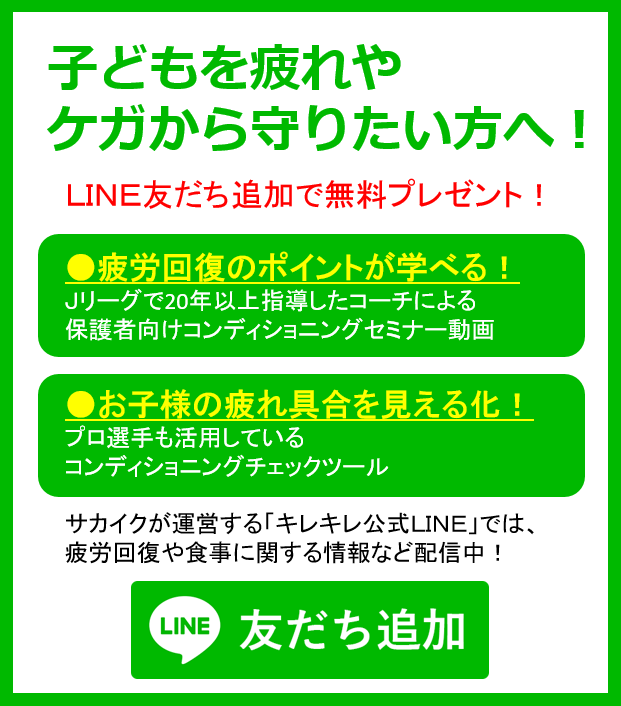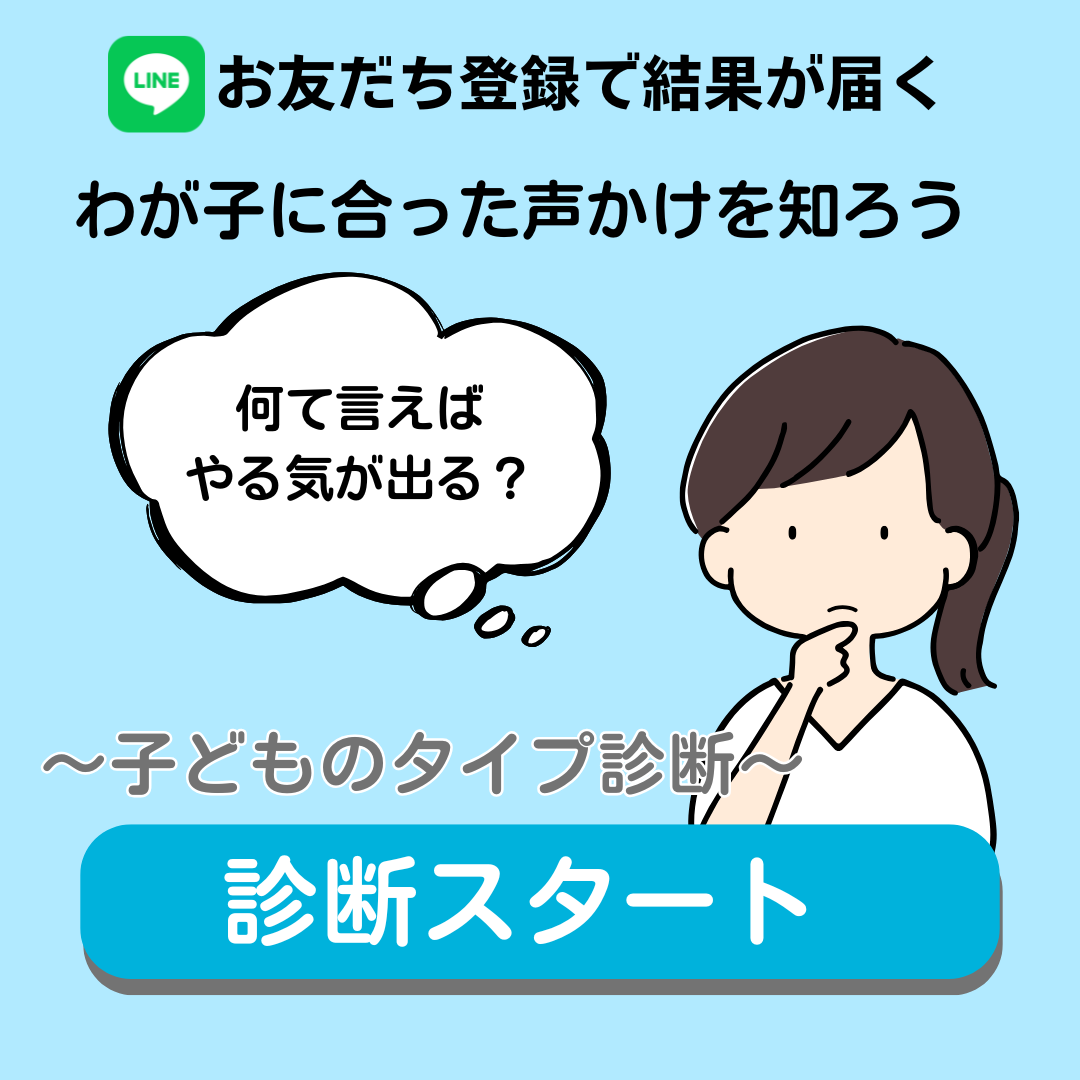健康と食育
サッカー選手の怪我予防にはクーリングダウンが大切!その役割とは?
公開:2013年4月18日 更新:2025年5月31日
キーワード:ストレッチマッサージ
日本代表のトレーナーとしても経験豊富な並木磨去光トレーナーに伺うコンディショニング講座。セルフコンディショニング、ウォーミングアップと、現場での実体験を交えながら学んできましたが、今回教えていただくのは「クーリングダウン」についてです。
「ウォームアップに比べると、クーリングダウンをしているチームはまだ少数派かもしれませんね。大人に比べれば次の日の影響が少ない子どもたちにも違いは感じられるはずです。いい習慣を身に付ける意味でも今からやっておいて間違いはありません」
ウォームアップに比べて馴染みがないかもしれませんが、筋肉の疲労を取り除き、次の日に備え、最善のパフォーマンスを引き出すのがクーリングダウンの目的です。効果の実感が薄くてもケガ予防や次の練習に向けて「試合後の5分でもやったほうがいい」と並木さんは言います。今回は、なるべく短時間でできる最低限のクーリングダウンを、その効果とともに教えてもらいましょう。
■血流とともに乳酸を流す クーリングダウンの役割
筋肉の疲労をとるというと、マッサージを思い浮かべる人もいるかもしれません。並木さんによると疲労原因物質のひとつとされる乳酸はマッサージでは除去できないそうです。
「マッサージは筋肉のハリや緊張を取り、ほぐすのには向いています。クーリングダウンは疲労をとるのが目的ですからそれよりも有酸素運動やストレッチが効果的でしょう」
クーリングダウンに最適なメニューは軽いジョギングとストレッチ。ジョギングはお互いに話ができるくらいのスピード、タッチライン=走る、ゴールライン=歩くくらいの負荷で十分。局所的なケガをしている場合などは同じ距離をゆっくり歩くだけでもいいそうです。
試合後はミーティングや後片付けなどやることもたくさんありますが、クーリングダウンの効果は運動直後であればあるほど高いという研究結果が出ています。体を動かした後は時間をとってジョギングだけでもするようにしましょう。
有酸素運動で全身の血流を流したら、次はストレッチです。このストレッチも血流を良くするのが目的です。筋肉を収縮させることで、血液の流れを作り、乳酸を一緒に流してしまうことを目的にしています。
■どっちもストレッチ? ウォーミングアップとクーリングダウン
「あれ?ウォーミングアップでもストレッチするよね?」
気になったあなたは大正解! そうです。ウォーミングアップ時にするストレッチとクーリングダウンでするストレッチは目的も性格も違います。
「この違いは重要です。これを説明することでクーリングダウンのストレッチの説明になるでしょうね」
並木さんもこの違いを重視しています。
「ウォーミングアップのストレッチは以前ご紹介したように、主に筋温を上げるために行います。よしこれから頑張るぞ! という刺激を身体に入れてサッカーモードへのスイッチを押す役割ですね。反対にクーリングダウンのストレッチはスイッチを徐々に切っていくためのものです」
大きな動力を必要とする機械は、いきなり主電源を切ってしまうと壊れてしまうものもあります。激しいトレーニングや試合の後は徐々に身体を休めていかないと、疲労が残り、次の起動に時間がかかってしまうのです。 一口にストレッチと言っても、場面や得たい効果によって種目も自ずと変わってきます。このように、目的に応じた適切な方法を選ぶことがサッカーにおける怪我予防には効果的です。また、クーリングダウンを習慣化することで、サッカー選手の怪我予防につながるため、日々のトレーニングと併せて、適切なコンディショニングを心がけましょう。では、ウォームアップとクーリングダウンのストレッチでは、どんな変化をつけたらいいのでしょう?
次回は実践編として具体的な種目の違い、やり方の違い、ポイントなどをご紹介します。練習前、試合前、たくさん試合が続いたときはどうすればいいのか?などなど、現場での経験豊富な並木さんに、無理なくできるクーリングダウン実践編をたっぷりと聞いてありますので次回もお楽しみに。
■サッカーで起こりやすい怪我
では最後に、サッカーにおいてどういった怪我が起こりやすいのかをご紹介します。怪我を予防するためにも把握しておくことが大切です。怪我は、外傷と障害の2つに分けることができます。外傷とは、外から大きな力が一度にかかることで起こる怪我のことで、骨折や捻挫、打撲、肉離れなどが挙げられます。また、障害は軽い力が持続的に同じ部位にかかることで発生する怪我です。疲労骨折や関節炎などが挙げられます。
ここでは、怪我の中でもサッカーでよく起こる捻挫、打撲、肉離れの概要と怪我予防の方法を紹介します。
■捻挫
捻挫は、関節に外から力がかかることで、靭帯などが損傷することです。捻挫をすると足首が腫れ上がる他、歩くだけでも痛みを伴うケースもあります。
なお、捻挫には大きく分けて3つの程度があります。もっとも軽いものは靭帯が伸びた状態で、1週間程度で治るとされています。次に中程度のものは靭帯の一部が切れた状態で、回復までに2〜3週間程度はかかります。そして、もっとも重い状態は靭帯が切れた状態で、回復には1ヶ月以上の時間が必要です。
サッカー選手の場合、足首の捻挫が多いため、プレーをする際にはバンテージやテーピングを巻く、プロテクターを着用するといったことが予防法となります。
■打撲
打撲は、打ち身とも呼ばれ、皮下組織や筋を損傷している状態のことです。患部に内出血が起こり変色することもあります。サッカーをプレーする以上接触は避けることができず、打撲を完全に回避することはできません。そのため、打撲が起こった時に速やかに応急処置を行えるように準備することが大切です。
■肉離れ
肉離れとは、筋肉が部分断裂を起こした状態のことです。筋肉が伸ばされた状態で収縮することで発生します。肉離れの程度によっては歩行が困難になることもあり、復帰までに時間がかかる可能性もあるでしょう。
サッカーの場合、ストップアンドゴーの動作を繰り返すほか、切り返しも多いため、ハムストリングや大腿四頭筋の肉離れが多く見られます。予防法としては、プレーをする前にしっかりとストレッチを行うこと、プレー後はクーリングダウンを行い、自宅でもストレッチやマッサージを行って体の柔軟性の維持・向上に努めることが大切です。
並木磨去光 //
なみき・まさみつ
日本代表アスレチックトレーナー。スポーツマッサージ・ナズー代表。トレーナーとしてW杯、五輪日本代表をサポート。ケガ人の治療、マッサージによる疲労の回復、コンディショニング、リハビリテーションなどを担当。今年行われたAFC U-16選手権では久しぶりにアンダーカテゴリーのトレーナーを担当。チームの準優勝、2013年に行われるU-17W杯出場権獲得に貢献した。
疲れやケガから子どもを守る方法とは?LINEで配信中>>